いやあ、これ、ココに置いていいものなのか?と思いつつ。
ssまとめるついでに、書き足してみました。
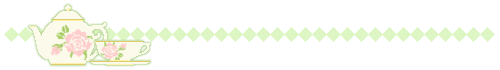
Precious ―ふたりでお茶を―
|
やはりというかなんというか、翌朝の高耶は、壮絶な仏頂面をしていた。 元々照れ屋の彼のこと、自分と一線を超えたのが急に気恥ずかしくなったのだろうと、 直江は努めてそ知らぬ振りをし、昨夜のことを口に出すのも控えていたのだが。 眉間に縦皺寄せながらそれでも何事もなかったかのように起き出だそうとする彼を前にしては、 そうそう黙ってもいられない。おもねるように申し出た。 「お願いだから、まだ休んでいてください。……身体、辛いでしょう?」 ところが、彼は。 「平気。今、ご飯の支度するから」 痛みに顔を顰めているくせに、平然とベッドから降りようとする。 「高耶さん!」 あくまで強がる態度に堪りかねて、つい声を張り上げた。 「それぐらい私がします。あなたは此処で寝ていなさい。いいですか?これは家主命令ですからね」 「………」 無言のまま見上げてくる恨めしげな上目遣いが凶悪なまでに可愛らしい。 「……キッチンはオレの領分だって決めてたのに」 やがてふいっと視線を逸らしてそんなことを呟くから、 もう愛しすぎてどうしたらいいか解らなくなる。 「お願いだから、今日だけは私にさせて。これからずっと一緒に暮らすんです。 無理したら続くものも続きませんよ?」 優しく諭しながら頭を引き寄せ、その額にキスをひとつ。 そうしてしぶしぶ頷くのを見届けてから寝室を後にしたのに。 朝食を用意して運ぶそのわずかな隙にも、高耶は、 トイレだシャワーだと理由をつけてはベッドを抜け出し、 あげく廊下で遭難しているところを直江に連れ戻される始末だった。 「まったくあなたときたら……。なんだってそんな無茶ばかりなんです? たった半日おとなしく寝てる、その我慢が利かないんですか」 もう信用ならないとばかり、片付けもそこそこにして直江はベッドに張り付いた。 「だって、さ…」 呆れ果てた口調に対し、高耶はいささか歯切れが悪い。 ごそごそと気まずげに上掛けを口元まで引き上げて、傍らの直江を見上げる。 その縋るような眼差しがやっぱり強烈に可愛らしくて、つい直江も眦を和らげ、今度はやわらかく問い返した。 「だって、なに?」 「辛そうにしてたら、おまえ、遠慮するじゃん?」 「はい?」 「やっと、コイビトになったのに。イタイだのしんどいだのオレが泣き言いったら、直江、やっぱり止めておきましょうね、なんて、シなくなるじゃん? それがヤだったんだよ!」 予想もしなかった台詞だった。 一方の高耶は、口にしたことで逆に踏ん切りがついたらしい。声も出ない直江に向ってさらに畳み掛ける。 「そりゃ少しはきつかったけど。でもそれだけじゃなかったから。その……またシてもいいかななんて思ったから。 朝になっても普段どおり何でもないってことアピールしなきゃって思ってたのに。 オレの身体ってば、全然思い通りになんねーし。結局おまえにも心配かけるし。畜生、ほんとカッコわりい」 溢れる言葉とともに感情が昂ぶったのだろう、いつのまにか涙目になった彼は、 直江の視線から顔を隠すように勢いよく上掛けを引っかぶってしまった。まるで拗ねた仔猫がするように。 呆然としてそんな高耶を見つめていた直江の顔がじわじわと笑み崩れた。 今朝の不機嫌も不可解なほどの意地っ張りも、元を質せば根っこはひとつ。 自分を想ってくれるゆえからだと、はっきり高耶の口から聞けたのだから。 「高耶さん……」 吐息のように囁いた。 「ありがとう。嬉しいです……」 そうして、上掛けごと高耶の身体を抱きしめる。 不意打ちの抱擁に、やっぱり猫みたいに高耶はじたじたと暴れたけれど、やがてそれもおとなしくなる。 ちらりと目元だけを覗かせ、それを待ち構えていた直江に微笑まれて赤くなった。 「私も遠慮なんかしないけど。あなたも遠慮しちゃダメです。 教えて。今の私にあなたは何をしてほしいの?」 観念して目を瞑った高耶がふくされたようにぼそりと呟いた。 「……このまましばらく枕やってて。できるかどうか解んないけど、少し眠って体力回復するから」 「了解」 少し腕を緩めてやると、心得たように高耶が身じろいで具合のいい位置に落ち着いた。 「んじゃ、オヤスミ」 「おやすみなさい」 最初緊張気味だった息遣いはすぐに穏やかな寝息に変わる。 自分の腕の中、最愛の人が安らいでくれるのを、直江は、息潜めるようにして見守っていた。 この人の目が覚めたら。 今度こそおいしいお茶をふたりで飲もう。 ふたりで過ごす幸せな時間が繰り返し、この先何時までも続くように。 ひそやかな願いをこめて。 |
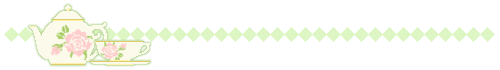
40年近く前だと思うのですが
萩尾御大の短編にエスパーものの三部作あってそれの最後のタイトルが
確か「みんなでお茶を」だった。。。
あのイントロ部分の優しげなイメージがこのふたりにも何時までも続けばいいなあと思います
BACK