お父さんは単身赴任。高耶さんはそのまま直江の部屋に寄宿しているという設定で、どうかよろしくです。
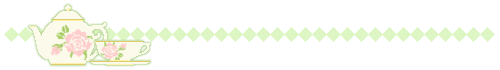
Precious ―ハツコイ―
|
アルミパックの茶葉の封をハサミで切ったその瞬間、きつめの香りがぷんと鼻をついた。 胸の奥が疼くような檸檬の芳香。 そして、微かに青さを感じさせるレモングラスの香り。 (うっひゃあ!) ダブル効果の甘酸っぱさに、思わず高耶は心の中で悲鳴をあげた。 (そりゃ、そう書いてあったけどさ。でもこんなにスゴイなんて思わないじゃん……) なぜか自分で自分に言い訳しながら、丁寧に茶葉の分量を量り、少し考えてから、その量を倍に増やしてポットに入れた。 折しもしゅんしゅんと湧き出したやかんの湯を一気に注いでふたをする。 指示されている抽出時間は二分半から三分間。 その間に硝子のサーバーにたっぷりと氷を詰めた。 こうしてしばらく蒸らされたお茶は、めりはりのきいたハーブの香りが緑茶特有の香気にやわらげられて、ふわふわとした綿菓子のような湯気を立ちのぼらせる。 二倍の濃さのそれを氷の上に注げば、程よく冷えたアイスティーの出来上がりだ。 お揃いの硝子の茶器と茶受けを用意して、準備万端整えてから、高耶は直江の私室のドアを叩いた。 「直江〜、お茶淹れたけど、こっち持ってくる?向こうで飲む?」 仕事の邪魔をしないよう、控えめないつもの問いかけ。 そして、返る応えはいつも同じ。 「もちろん、向こうで一緒にいただきますよ。高耶さん」 それでも今日は、にっこりと振り返る直江の顔がなんだかやけに眩しくて、思わず目を伏せてしまった高耶だった。 「今日さ、おばさんと冴子さんに贈るお茶買いにあの店に行ってきた。んで、これはうち用。 今の季節限定だっていうから、つい買っちゃった。……五日ぐらいで飲みきると思うから。 だから、もしも気にいらなくても我慢してつきあって。お茶受けはレアチーズケーキ。その……レモンの風味に合うかなあ………なんて」 いつもとは違う茶葉を買ってしまったことを気にしているのだろうか。 一気にまくしたてる高耶を柔らかな笑顔で直江がみつめ、その視線にてれたように俯きがちになるのを、励ますように口を開いた。 「爽やかな香りですね。色も涼やかで香りにとても似合っている。緑茶にこういうフレーバーがあるとは思いませんでしたが。でも美味しいです」 「ほんとに?ほんとにそう思う?」 一口飲んで感想を言う直江に、高耶ががばっと身を乗り出す。やけに真剣なその様子が目に愉しくて、さらに歓ばせようと言葉を継いだ。 「ええ。ほんとに。それになんだかこのお茶は、高耶さんに似てますね」 他意はなかった。清々しい清涼感が伸び盛りの若木のようで。高耶を彷彿とさせたから、何気なく添えた言葉。 なのに、その一言で、高耶は真っ赤になって絶句する。 「高耶さん?」 あまりに過剰な反応に、直江の声が跳ねあがった。 そういえば、今日の高耶はどこかおかしい。新しい味に挑戦してみた、どうやらそれだけではないようだ。 眉顰める直江に、頬に赤みを残したままの高耶が、わたわたと両手を振ってみせる。 「なんでもないっ!本当になんでもないから。その……気にいってもらえたならいいんだ。その、オレの気持ちだから。つーか、選んだ責任上、美味しいって言ってくれてすっげー嬉しいし。 だから、温くならないうちにお代わりしよっ。な?」 これ以上は問い詰めてくれるなと、あからさまに話題を逸らそうとするその様がいじらしくも可愛いらしくて。 直江はかなりの不審を残したまま、それでも大人の余裕を見せようと苦笑を浮かべておとなしくその勧めに従ったのだった。 謎が解けたのは一週間後。 外出の折りに、偶然、例の紅茶専門店を通りかかった。 そういえばあのレモンのお茶はなくなってしまっていたなと、ふと思った。 季節限定といっていたから、たぶんこの機会を逃せばまたしばらくは味わえないだろうとも。 高耶もずいぶんと気にいっていたようだし、お土産に買っていったら喜んでくれるかもしれない。そう考えたらもう矢も盾もたまらなくて自動ドアの前に立っていた。 店内に足を踏み入れながら、肝心のそのお茶の名前を知らないことにも気づいたけれど、あれだけ個性的なブレンドはスタッフに尋ねればすぐにわかるに違いない。 ひとに訊くまでもなくあっさりと目当ての品はみつかった。 鮮やかな翡翠のブレンド。添えてあるカードには青いレモンの香り云々と説明書きがされてる。 けれど、本当に驚いたのはそのネーミング。 ケースの前に佇んで、直江は暫く動かなかった。さまざまな疑問が淡雪のように溶けて胸に染み入る。 初めてこのお茶を出してくれたときの、高耶の挙動不審の意味が、ようやくすべて氷解した。 (そういうことだったんですね、高耶さん) こみあげる笑いをかみ殺しながら、直江は目線でスタッフを呼ぶ。 「これを……」 指差したレモンの香りのお茶の包みには、ラベルに『ハツコイ』と銘打たれていた。 買い求めたお茶を、直江は高耶には渡さず、自室の引き出しにしまいこんだ。 どんな気持ちで彼がこれを選び、自分に飲ませてくれたのか。 ……彼の告白と受け止めるのはただの自惚れだろうか? 時々、その包みを眺めては、頬緩ませながら考える。 おそらく彼はこのお茶の名を自分に知られるのを望んでいない。彼は今、ひどく天邪鬼な年頃だから。図星を指したら憤死してしまいかねない。 それでも、ひとつの行動として表してくれたそのことが嬉しくて。 封を切らないお茶の包みは、タイムカプセルのように青い香りを閉じ込めたまま、今も直江の机の奥に隠されている。 |
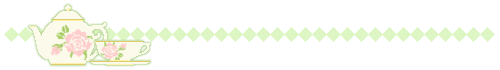
とある方がくださったお茶の名は「ハツコイ」とありました。
青いレモンの香りにもうめろめろ。まるでメロンパンナちゃんの最終兵器をくらったよう…(笑)
このお茶は高耶さんだっ!!絶対直江に飲ませなくてはっっ!!と、
妙な義務感で書き留めた煩悩です。
Yさま。煩悩のネタ、どうもありがとうございました<(_ _)>
BACK