|
「かっげとらぁ!久し振りぃ!ここよ、ここ!」
予約した旨と連れの名前を伝え、オーナーらしき年配の女性に案内されてオープンテラスへと足を踏み入れたとたん、けたたましい歓声が響き渡った。 「もうすっかり具合はいいの?それだったら連絡ぐらい入れなさいよ。まったく薄情なんだから、あんたって子は。ひとがどれだけ心配したか判ってんの?」 思わず逃げ腰になって後ずさる高耶に駆け寄り、その胸ぐらを掴まんばかりにぽんぽんと畳みかける彼女の眼には、すでに周囲の人間は映っていない。 「ち、ちょっと、ねーさん……落ち着けって。そんなに喚いたら周りにめーわくだろ?貸切って訳じゃないんだから」
綾子を引き離そうとあがきながら、高耶が申し訳なさそうにちらりと傍らに眼をやった。 「あ……、ごめんなさい。あたしったら。つい声を張り上げちゃって……」 赤面しながら、高耶にではなく、婦人にぺこりと頭を下げた。 「まったく……。どうもすいませんねぇ。見境なくなっちゃって……」 その綾子の背後から手が伸びて、くしゃりと髪をかき混ぜながら話を引き取ったのが千秋である。 「目の前で事故られて、旅先の病院で三日も付き添って看病してやった揚げ句に、親元にかっさらわれて音沙汰なしですからね。そりゃあこいつの保護者からは感謝されましたけど、本人からは無しのつぶて。いくらこいつが身内でも、やっぱり筋は通してもらわないと……ねぇ?」 嘘は言っていないのだが、他人が聞いたらまず百パーセント違う状況を想像するであろう説明をさらりと口にして同意を求める千秋に、婦人の笑みはますます深く、慈愛に満ちたものになった。 「さて、最後の一人がもうそろそろ来るはずなんです。……おまえら一緒だったんだろ?直江、クルマ置きにいったのか?」 「うん。前が一杯だったから、別のとこに停めてくるって…」 住宅街にあるせいで、敷地にゆとりのないこのレストランでは少々離れた場所に駐車場を確保しているのだった。 「じゃ、あと七、八分ってところかな?料理はそいつが着いてからということで……」 「かしこまりました」 いつのまにか、すっかりその場を仕切ってしまった千秋に深々と頭を下げた後、婦人は内緒話をするように小声で付け加えた。 「テラスには今日は他のお客様はいらっしゃいませんから……、多少賑やかでも構いませんのよ」 掛け値なしの好意に、千秋は極上の笑顔で応えると、あとの二人を促してテーブルへと戻った。
鉢植えの陰に入って、視線が遮られるやいなや、呆れたように綾子が言った。 「馬鹿野郎。あれだけ目立っちまったら、確かめるもんも確かめられなくなるだろーが。邪魔がはいらねーうちにさっさとやっちまいな」
言い返す千秋の表情は、先程までの好青年の笑顔は消え、いつもの人を食ったものになっている。 「な、なにを……」 「いいから素直に脱ぎなさい。傷の様子が見たいのよ。あれだけ世話を掛けさせといてまさか否とは言わないわよねぇ?」
さすがに声はひそめているが、その分、抗いがたい迫力がある。 「ちょっとねーさん……そこは関係ねーだろ……」 身を屈めた綾子の後頭部を見下ろしながら、肩に手をかけて押しとどめる。 「ないわね……」 ポツリと声が洩れた。 「……のようだな」
傍らから、茶化すような千秋の相槌が聞こえる。 「なんでないわけ?あんた、ゆうべ昨夜直江んちに泊まったんでしょ?それなのに、どうしてキスマークのひとつやふたつつけてないのよ?」 「な・な・何を……」
体中の血液が沸騰する思いだった。 「これじゃ、賭けになんないわね」 いかにも残念だ、という響きをにじませる綾子に、千秋が肩をすくめてみせた。 「仕方ねーな。今回はお流れだ」 「ちっ、絶対あちこちにつけまくってると思ったのになー。御寿司食べそこねちゃった」 「あほう。それはこっちの台詞だ。こんなことならもっと条件を甘くしておくんだったぜ」 「何言ってんの。痕が残ってるとこまでは、同意したでしょ」
血の上った頭にもようやく事の次第が飲み込めてきた高耶に、追い討ちをかけるように綾子が解説をしてくれる。 「痣の数で週末の夕飯賭けてたのよ。全然ないなんて予想外だったわー。喧嘩でもしたの?」 「プライベートに首を突っ込むのは遠慮してもらおうか」
突然、葉陰越しに固い声が降ってきた。 「時間切れだな……」 ぼそりと言った千秋にも、直江はきつい視線を投げかけた。 「いまさら、夕飯を賭けることはないだろう?只メシを食うのはお手のものだろうに」 催眠暗示とたらしの才能を皮肉ったのだが、千秋は動じない。 「ばーか。おまえらに奢らせるから美味いんだろうが。今日の名目は、景虎の全快祝いだからな。勘定の方は頼んだぜ」 そう言って、さっさと席に戻ってしまった。 「じゃ、そういうことで。ほら、景虎も行くわよ。あんたが主賓なんだから」
そそくさと綾子も後に続く。
「恋人っていうよりは若衆を随えた姐御だな、ありゃ。景虎もああしてると普通のガキにしか見えねーのにな。……あんまり苛めんなんよ?」 さりげなく付け加えられた一言に直江がふと視線を上げる。 「気づいていたのか?」 「あれだけおまえの念がこもってりゃな。襟足のあたり、髪に隠れているはずの鬱血の痕がきれいに透けて視えた。晴家だって気づいたはずだ」 「……賭けは無効といわなかったか?」 「気づかないふりをして坊やのプライドを守ってやるのもオトナの余裕ってもんだ。秘め事がばれたら憤死しかねない性格してるしな」 そんなとこがけっこう気に入ってんだ、と、小さく呟いてからまっすぐに直江を見る。 「でもおまえが景虎をかまう理由は違うだろ?…さっきの真っ赤になったあいつの顔、自覚してない分、悩殺ものの艶っぽさだったからな。あんな顔、他の誰にも見せたくなくてべったり張り付いているんだろうが?だったら少しは加減してやれ」
こうも直言されては仕方がない。 「判っているなら、何もあそこまで遊ばなくてもいいだろうに…」 つい恨み言が口をつく。
おかけで食事の間中、高耶の態度はぎこちなかったのだ。 「刺激のない人生には飽き飽きしてるんでな。壊れない程度にはじゃれつかせてもらうさ」 さらりと恐ろしい台詞をはいて、おもむろに千秋は腰をあげる。 「さてと…、そろそろ助けに行ってやらないと。景虎のやつ、お茶の呑み過ぎで腹くだすぞ。晴家、やたらに気合が入っていたからな」 「違いない」 そうして高耶たちと合流すべく、ふたりはテラスを後に花盛りの庭へと降りていった。
|
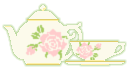
番外へつづく
唐突な始まりですがこれには訳があります。
最初に書いたのは「夜の想い」にあたる部分で、実はこれが全部ベッドシーンだったのです(…)
これはかわら版で配布するのはまずいと思い、差し替えに書き足した昼の部分がこの掌編「昼の貌」です。
千秋や綾子ねーさんは書いててすごく楽しかった!(笑)調子に乗って、ルバーブネタの番外まで出してしまいました。
文中に「怪我云々」とあるのは、調伏時に高耶さんが負傷した別の話と設定(時間軸?)が同じだからで…。
そのうちこちらの和綴じの一連の話もUPできたらいいなと思っております。
BACK
